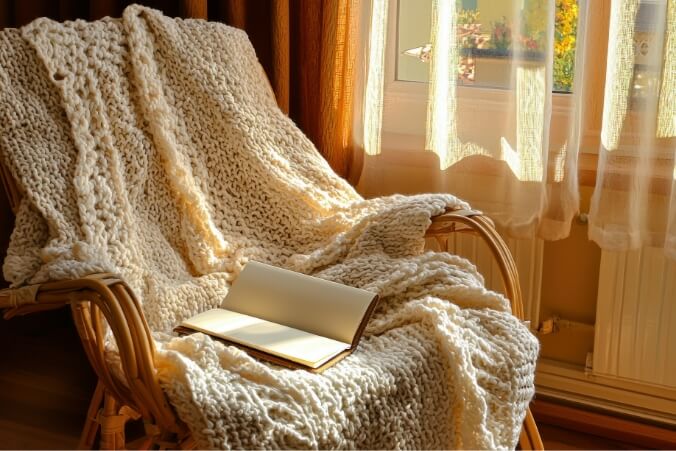「正しさ」とは、どこからやってくるのでしょうか。
マネジメントの場面で、「こうすべき」と言い切った後に、ふと違和感を覚えることがあります。言葉は正しい。理屈も通っている。それでも、どこか自分の感覚とずれている。その感覚に気づいたとき、私たちは問いの入口に立たされます。
“その正しさは、自分の中から湧き上がったものだろうか?”
判断が他者の期待や過去の常識に引っ張られているとき、自分の内側にある“ずれ”は、小さな違和感となって表れます。それは、抑えられていた自分自身の価値観が、そっと声を上げた瞬間かもしれません。
マネジメントとは、自分の判断にどれだけ一貫性を持たせられるか、という営みでもあります。ただしここで言う“一貫性”とは、「常に正しいことをする」ことではありません。むしろ、自分の価値観に根ざした選択を、迷いながらも続けられるかどうか。その問いかけに対して誠実であることです。
心理学では「内的一貫性(internal consistency)」という言葉があります。これは、私たちの動機づけや信頼感と深く関係しています。自分の判断に納得できること。そこにこそ、行動の力強さが生まれます。
では、私が「正しい」と思っているその判断は、いったい誰の、どんな価値観に基づいているのでしょうか?
違和感は、間違いのサインではありません。
むしろ、自分が守りたいものを思い出させてくれる、静かなアラートです。
正しさを問うということは、自分の判断の起点をたどること。
そこに触れることで、「私は何を大切にし、何を手放したいのか」が見えてきます。