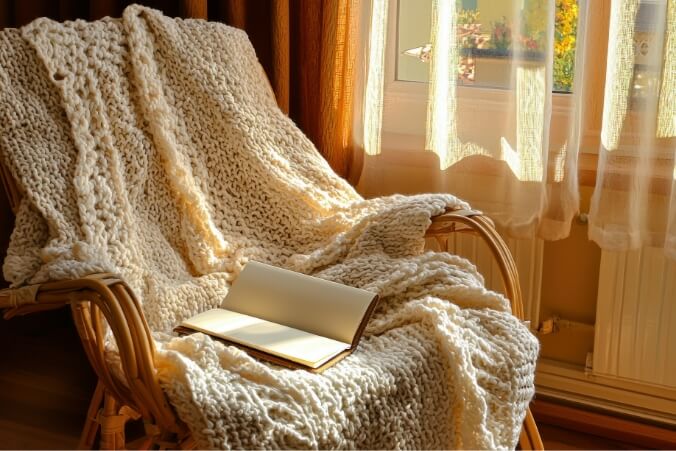つながりを求めながらも、うまく表せない自分
関係志向性とは
「周囲との関係づくりが苦手かもしれない」と感じたことはありませんか。会話に入りにくかったり、相手との距離感を測りかねたりする場面は誰にでもあるものです。
関係志向性とは、人とのつながりを求め、信頼や安心感を育む力のことです。Emotional Compassでは「関係管理」(RM)に属する特性であり、チームや組織において協力や信頼を支える基盤になります。
リーダーにとっても、この力はメンバー間の結束を強め、安心して働ける職場づくりに直結します。
研究が示す人の「つながり欲求」
心理学者ロイ・バウマイスターとマーク・リアリー(1995)は、「人は関係を求める存在(belongingness hypothesis)」であると主張しました。人間は孤立すると心理的にも身体的にも不利益を被りやすく、逆に良好な関係を持つと幸福度や健康が高まるとされています。
また、ハーバード・ビジネス・レビューの記事「The Power of Belonging」(2019)は、職場における「帰属意識」が従業員のモチベーションとパフォーマンスを大きく左右することを示しました。
さらに、最上雄太(2025)『人を幸せにする経営』でも、共感や関係性の質がリーダーシップの基盤であることが強調されています。これらの知見は「関係志向性」が個人の幸せや組織の成果に直結することを裏付けています。
実践のためのレシピ
関係志向性が低めの人でも、次の工夫で関係づくりを前向きに進められます。
- 小さな共有から始める
日々のちょっとした出来事を話題にしてみるだけで、関係の入口ができます。 - 相手の強みに注目する
会話で「その考え方、いいですね」と相手を肯定する言葉を添えると信頼が芽生えます。 - 1対1の対話を大切にする
大人数の場では話しづらくても、個別に声をかけると深い関係を築きやすくなります。 - 日常のやりとりに一言を添える
業務の最後に「ありがとう」「助かりました」と伝えるだけで、自然に関係が温まります。
信頼を育むリーダーへ
リーダーにとって、関係志向性はチームの結束を高める力です。たとえ関係づくりが得意でなくても、「聞く姿勢」や「肯定の一言」 を繰り返すことで、メンバーは安心して意見を言えるようになります。心理的安全性が生まれると、失敗を恐れず挑戦する文化が育ち、組織全体の力が引き出されます。
あなた自身は?
あなたは普段、周囲との関係をどう築いていますか?
冷静さを保ちながらも、信頼を深める一歩を踏み出せる場面はどこにありますか?
あなたにとって、信頼を深める一歩はどんな場面に隠れていますか?
あなた自身の特性を確かめてみませんか?
Emotional Compass は、経営情報学博士である最上雄太が総合監修した EQリーダーシップ® を測定・育成するアセスメントです。
全24特性×3レベルの診断を通じて、あなたの「感情を活かす力」を客観的に把握できます。
👉 Emotional Compass の詳細を見る(2025年秋公開予定)
参考・出典
- Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation.
- Harvard Business Review (2019). The Power of Belonging.
- 最上雄太(2025)『人を幸せにする経営』(国際文献社)