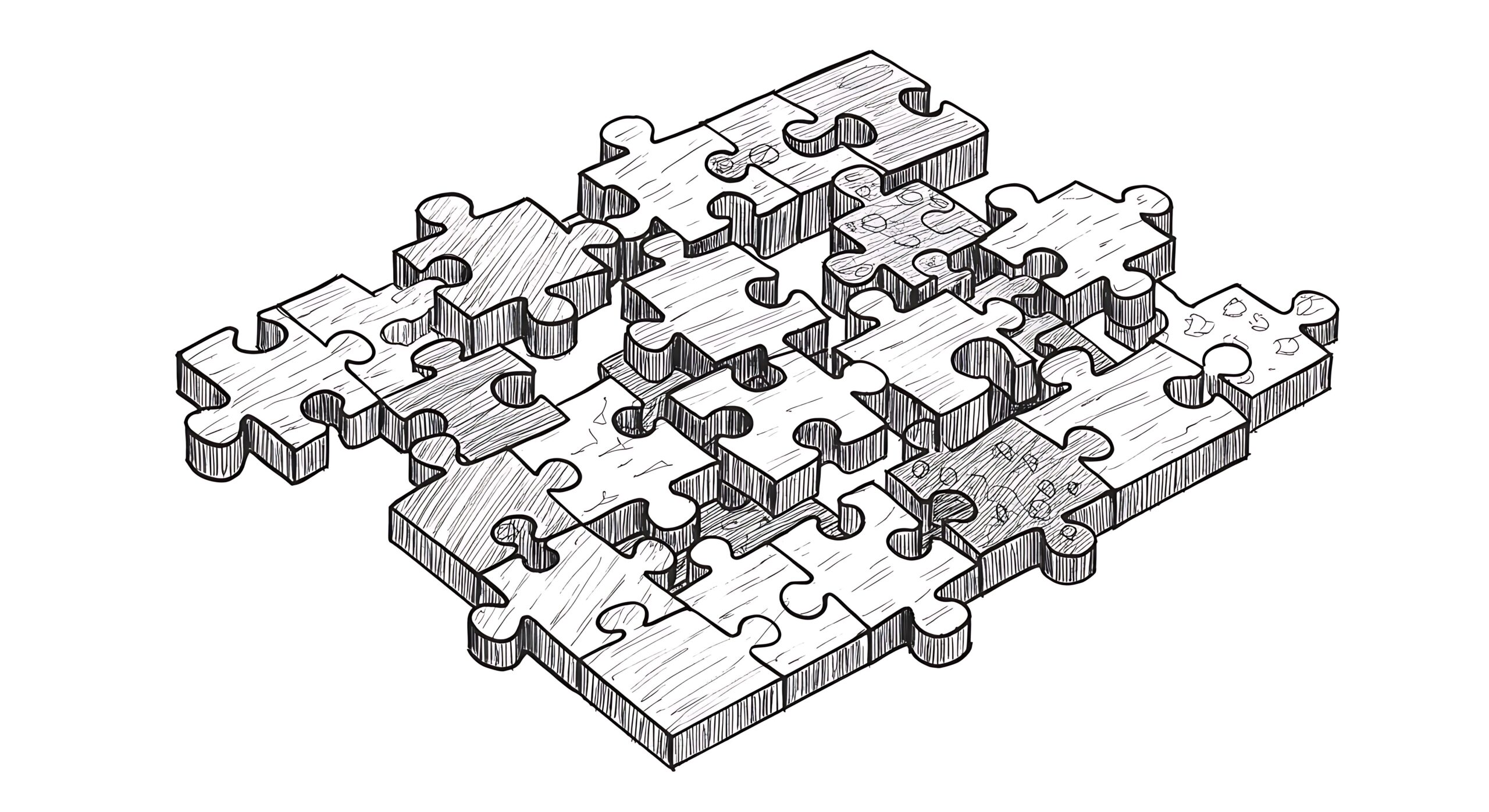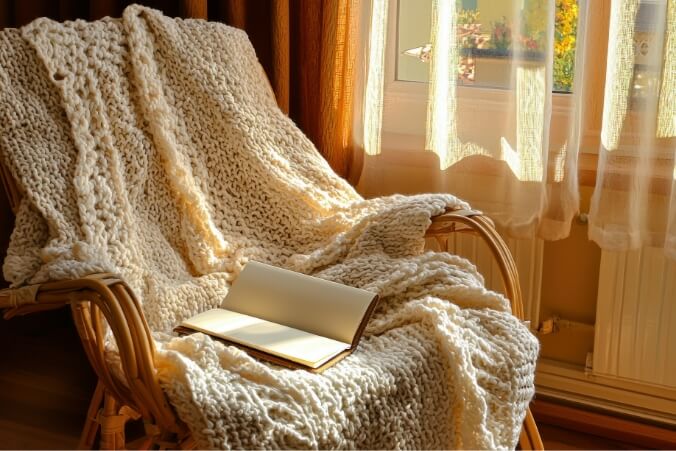停滞を打破するか、安定を選ぶか──リーダーは常にこの問いに直面します。
Emotional Compassでは、本特性は自己管理(SM)因子に属します。
慣れたやり方を続けることで安心感を得る一方で、大きな一歩を踏み出すには不安やリスクが伴います。その選択に関わる特性が「ブレイクスルー」です。
Compassでは「自己管理(SM)」の因子に属し、困難や停滞を越えて新しい可能性を切り開く力として位置づけられます。
イノベーションが起きにくい状況では、人は非連続的な変化に慎重になり、現状を維持しやすくなりますが、その裏返しとして堅実さや継続性に強みがあります。リーダーにとってブレイクスルーは、大きな飛躍を起こす力であると同時に、安定を守りながら組織に前進の流れをつくる力としても意義があります。
学びの視点
科学哲学者トーマス・クーンは『科学革命の構造』(1962)で、学問の進展が「通常科学」と「パラダイム転換(ブレイクスルー)」の両方から成り立つことを示しました。通常科学が日々の探究を通じて土台を固めるからこそ、やがて大きな転換が生まれるのです。つまり、常に大きな革新があるわけではなく、安定的な積み重ねが革新を支える基盤になります。
クリステンセンら(2008)は、ハーバード・ビジネス・レビューの記事「イノベーションを殺すもの:財務ツールが新しい挑戦力を奪う(Innovation Killers: How Financial Tools Destroy Your Capacity to Do New Things)」で、伝統的な財務指標が革新的な取り組みを抑制する危険性を指摘しました。企業は効率性や短期利益を重視するあまり、新しい可能性への投資を後回しにしてしまうことがあるのです。したがって、革新を実現するためには、日常の安定的な運営とともに、挑戦を継続的に支える仕組みを整える必要があると論じています(HBR記事)。
著者の最上雄太(2025)は『人を幸せにする経営』において、組織は「安定と変革のバランス」を取りながら成長することが重要だと述べています。また『シェアド・リーダーシップ入門』(2022)では、飛躍を導くためには日常の小さな工夫や協働の積み重ねが不可欠であると説かれています。
明日からできる実践法
- 小さな一歩を試す
大きな飛躍ではなく、小規模な実験や改善を通じて前進する。 - 既存資源を工夫する
手元にある仕組みやリソースを見直し、新しい組み合わせで活用してみる。 - 他者の視点を取り入れる
自分のやり方に固執せず、周囲の意見や異なる立場の人の視点を取り入れる。 - 停滞を共有する
「進まない」と感じたときは一人で抱え込まず、仲間と共有することで突破口が見えやすくなる。
まとめ
ブレイクスルーは、大きな飛躍や革新だけを意味するものではありません。弱めに表れるときでも、安定を大切にしながら一歩ずつ進む力として活かすことができます。リーダーにとって大切なのは「自分なりの突破口」を見出し、組織に前進の流れをつくることです。
👉 あなたにとって、いま越えたい壁はどんなものですか?
📘 さらに詳しく学ぶ
- 『人を幸せにする経営』(最上雄太, 2025, 国際文献社) → Amazonリンク
- 『シェアド・リーダーシップ入門』(最上雄太, 2022, 国際文献社) → Amazonリンク
- Emotional Compass公式サイト → innershift.jp/compass
✨ INNERSHIFTからのお知らせ
📘 公式サイト:innershift.jp
✍️ JOURNAL:innershift.jp/journal
🧭 Emotional Compass:innershift.jp/compass
🎥 YouTubeチャンネル:INNERSHIFT Channel
💼 LinkedIn:Yuta Mogami
🐦 X(旧Twitter):INNERSHIFT_JP
📘 Facebookページ:INNERSHIFT
参考文献
- Thomas S. Kuhn (1962) The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago Press.
- Clayton M. Christensen, Stephen P. Kaufman (2008) “Innovation Killers: How Financial Tools Destroy Your Capacity to Do New Things”, Harvard Business Review. → HBR記事
- 最上雄太(2022)『シェアド・リーダーシップ入門』国際文献社 → Amazonリンク
- 最上雄太(2025)『人を幸せにする経営』国際文献社 → Amazonリンク