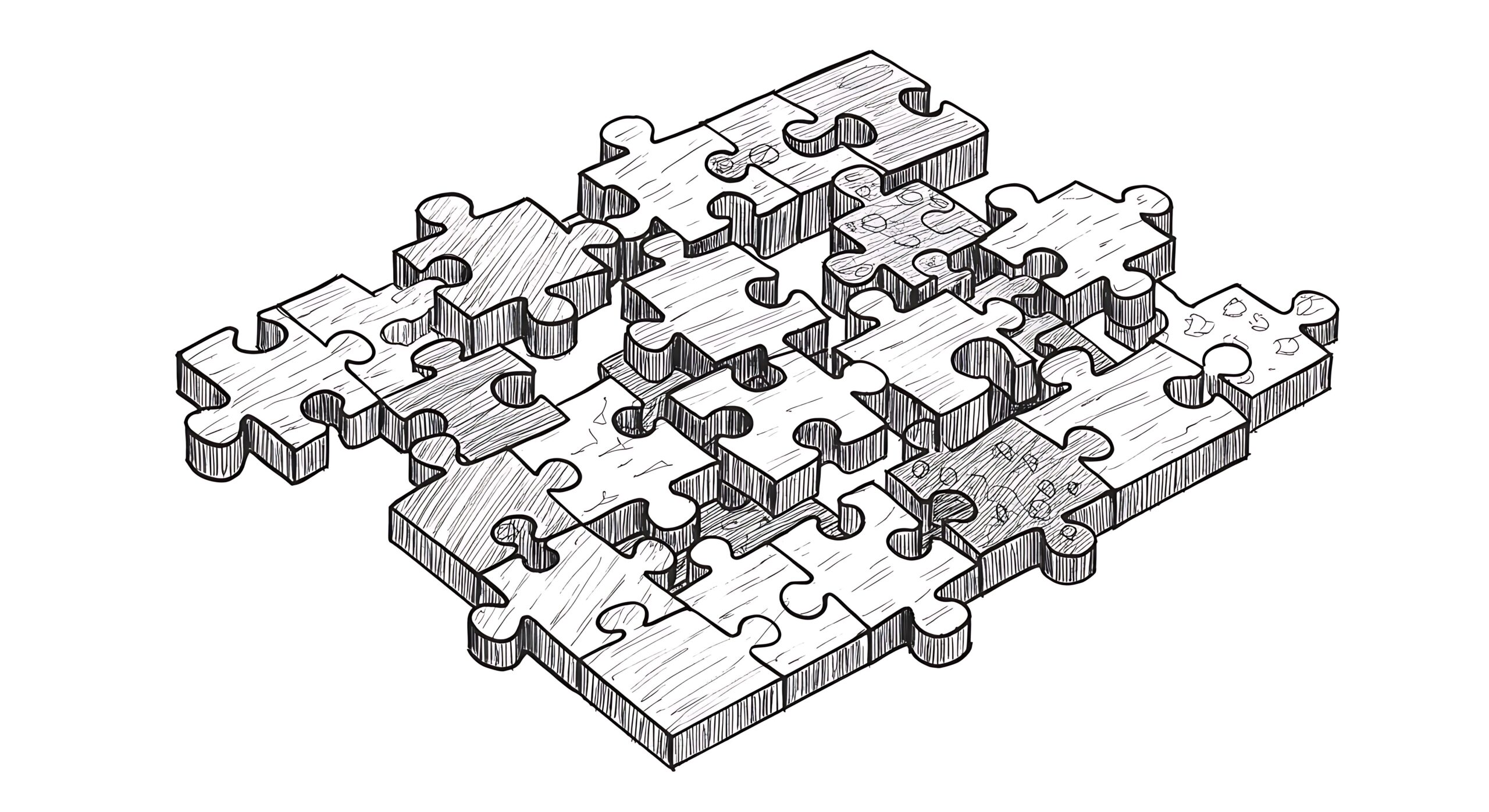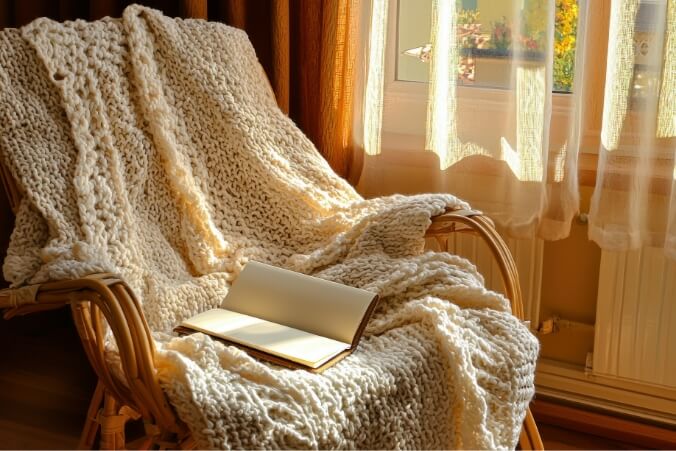誰もが仕事や挑戦の中で失敗を経験します。問題は、その失敗をどう受けとめるかです。小さなつまずきにも過敏に反応してしまうと、前に進むことが難しくなり、自責の念や停滞につながりやすくなります。
Emotional Compassでは、本特性は自己管理(SM)因子に属します。
「失敗受容力」とは、過去の失敗や挫折から学びを見出し、次の一歩の糧にできる力です。Compassでは「自己管理(SM)」因子に属し、リーダーの持続的な成長に欠かせない要素とされています。弱めの傾向があるときは、失敗を恐れすぎて挑戦できなくなったり、必要以上に自分を責めてしまったりすることがあります。しかし、裏返せば「高い基準を持ち、成果を真剣に捉える姿勢」とも言えます。
リーダーにとって失敗を受けとめる力は重要です。自らの失敗を率直に共有できるリーダーは、周囲に「ここで挑戦しても大丈夫」という心理的安全性を広げます。それが新しい挑戦や学びの文化を生み出す土台となります。
研究と実務が示す失敗受容の価値
心理学者キャロル・ドゥエックは、著書『マインドセット ―「やればできる!」の研究』(2006, Mindset: The New Psychology of Success)で「成長マインドセット(growth mindset)」という概念を提唱しました。これは、失敗や困難を才能の限界ではなく学びの機会ととらえる考え方です。挑戦の過程での失敗を肯定的に受けとめることが、自己効力感や長期的な成果につながるとされています。この視点は、リーダーが自らの失敗をオープンに語ることの意義を裏付けています。
工学者の畑村洋太郎は『失敗学のすすめ』(2005)において、失敗は避けるべきものではなく、積極的に分析・共有すべき対象であると説きました。畑村は、失敗を記録し、原因を解明し、他者と共有する仕組みこそが、次の成功を生み出す土壌になると述べています。これは「失敗受容力」を個人の姿勢だけでなく、組織文化の基盤として位置づける考え方と重なります。
著者の最上雄太(2022)は『シェアド・リーダーシップ入門』において、失敗を共有するプロセスがチームの相互信頼を強めると指摘しています。さらに『人を幸せにする経営』(2025)では、失敗を学びに変え続ける組織こそが、挑戦を持続できると述べています。これらは、失敗受容力が「心理的安全性」と「挑戦文化」を育む鍵であることを示しています。
明日から試せる実践レシピ
- 小さな失敗を共有する
ミーティングで「今日の小さな失敗」を1つだけ話す習慣をつくると、失敗を隠さずに扱える空気が生まれます。 - 学びを言語化する
失敗から得た気づきを一文で書き出すことで、自分の中に定着させやすくなります。言葉にすることでチームへの共有も容易になります。 - リトライ計画を立てる
同じ失敗を繰り返さないために、「次はどう行動するか」を具体的に書き出してみましょう。再挑戦のハードルが下がります。 - 失敗談を交換する
チームでお互いの失敗談を共有すると、信頼関係が深まり、挑戦を後押しする心理的安全性が広がります。
まとめ
失敗受容力は、単にミスを許す心の広さではなく、失敗を成長の糧に変える力です。弱めの傾向があるときには、失敗を過度に恐れて挑戦がしにくくなったり、自分を責めて停滞につながることがあります。しかし、裏を返せば成果に真剣で、基準を高く持つ姿勢の現れでもあります。
リーダーが失敗をオープンに語り、学びに変えていく姿勢を示すことは、チーム全体の心理的安全性を高め、挑戦する文化をつくります。失敗を隠さず共有できる組織は、試行錯誤を重ねながら新しい価値を生み出していくことができます。
👉 あなた自身の失敗体験から、どんな学びをチームに共有できますか?
📘 さらに詳しく学ぶ
- 『人を幸せにする経営』(最上雄太, 2025, 国際文献社) → Amazonリンク
- 『シェアド・リーダーシップ入門』(最上雄太, 2022, 国際文献社) → Amazonリンク
- Emotional Compass公式サイト → innershift.jp/compass
✨ INNERSHIFTからのお知らせ
📘 公式サイト:innershift.jp
✍️ JOURNAL(リーダーシップ特性記事):innershift.jp/journal
🧭 Emotional Compass(自己特性診断・2025年秋公開予定):innershift.jp/compass
🎥 YouTubeチャンネル:INNERSHIFT Channel
💼 LinkedIn:Yuta Mogami
🐦 X(旧Twitter):INNERSHIFT_JP
📘 Facebookページ:INNERSHIFT