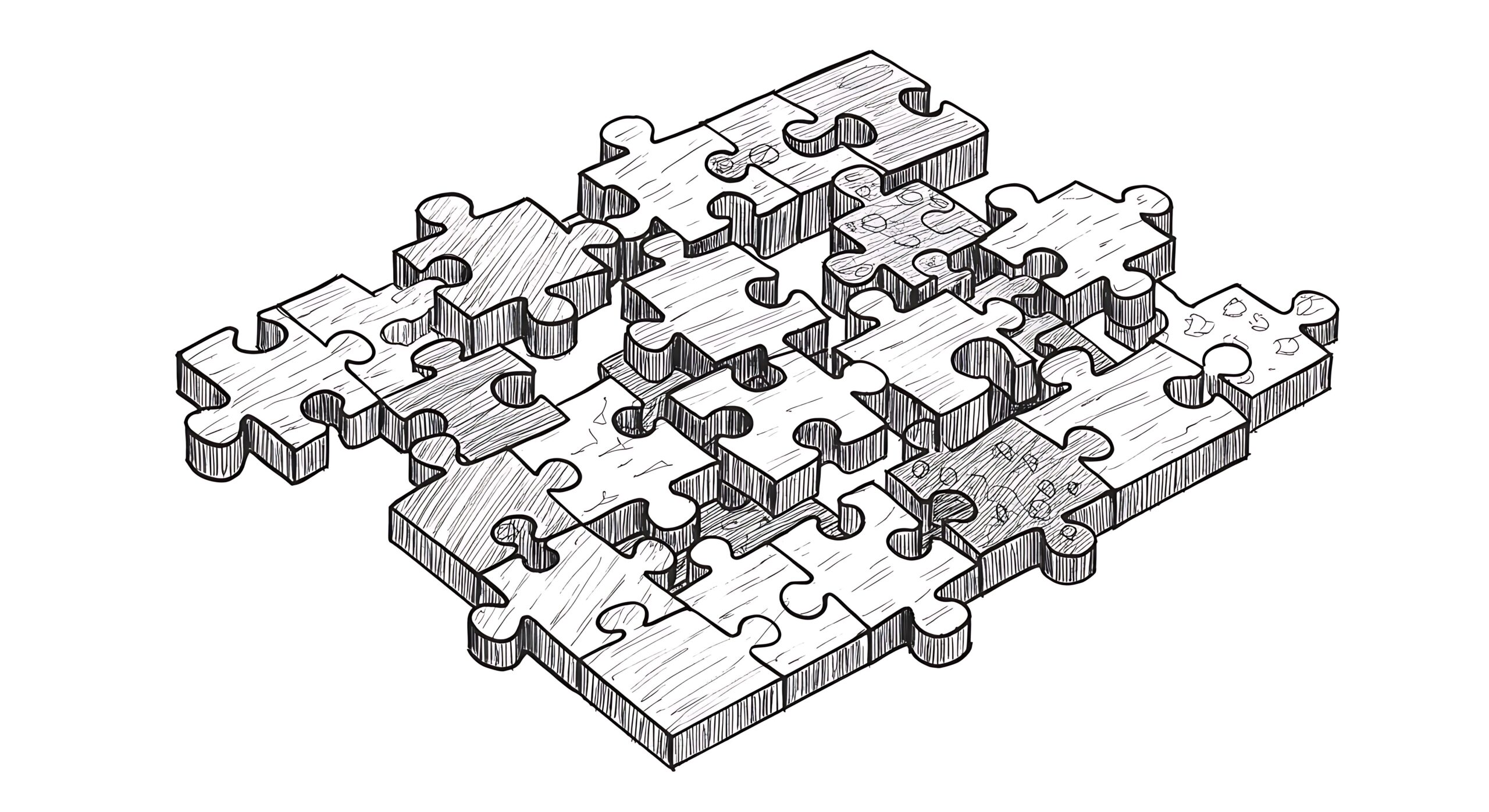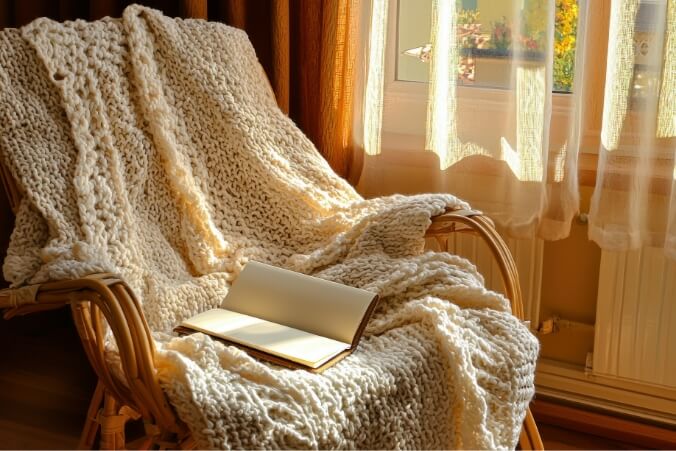朝、同じ景色を見ていても、となりの人が何を感じているかは、ほんとうにはわからないものです。同じ方向を歩いているのに、心に映っている風景は少しずつ違う。それでも並んで歩き続けること。そこに、人と関わる誠実さと成熟が宿ります。
「差異への耐性」とは、相手と自分が違う現実を生きていることを認めながら、それでも関係を続けていく力です。相手に合わせて同化することでも、相手を説得して同じにすることでもなく、“違いを抱えたまま共に歩む”姿勢です。
Emotional Compassでは、本特性は関係管理(RM)因子に属します。対話を通じて、違いの中に信頼を見いだす力――それが、成熟したリーダーのあり方です。
「同じ」ではなく、「違うまま関わる」
人は、自分と相手が“わかり合えている”と思いたい生き物です。けれど、ほんとうの関係とは「完全にはわかり合えない」ことを前提に築かれるものです。互いの考えや感情には、見えないずれがある。それを“誤り”ではなく、“差異”として受け止めるところに、成熟が生まれます。
リーダーの役割は、すべての意見を一致させることではありません。異なる視点を持つ人たちが、それぞれの考えを尊重しながら前に進むよう導くこと。差異への耐性とは、他者の違いを消さずに、関係を紡ぐ知性です。
「対話」は、思考を共有する場
ウィリアム・アイザックス(Isaacs, 1999)『対話する力(Dialogue and the Art of Thinking Together)』は、対話を「同意を得る場」ではなく、「共に考える場」として位置づけました。
「対話とは、他者とともに考える芸術である。」
この言葉が示すのは、“違い”を超えて一つの答えに収束するのではなく、違いの中で新しい理解を生み出すことです。他者の言葉に揺さぶられ、自分の考えを問い直す過程そのものが、対話の価値です。
違いは不安をもたらしますが、同時に思考を進化させる触媒でもあります。だからこそ、リーダーは「わからないからこそ話してみよう」と言える存在であるべきです。
「話し続けること」が信頼を育てる
最上雄太(2025)『人を幸せにする経営』(国際文献社)では、「話せば何かが生まれる」という言葉が繰り返し登場します。そこにあるのは、“相互理解”よりも“関係継続”への信念です。
理解できないままでも、話し続ける。一度の対話で解決を求めず、違いを抱えながら向き合い続ける。その姿勢こそが、組織に信頼を育てる土壌となります。
リーダーの誠実さとは、すべてを理解する力ではなく、理解できないものを抱えながらも関係を絶やさない力です。
「違い」を抱えて共に歩む
差異への耐性とは、理解よりも共存を選ぶ知性です。相手を変えるのではなく、自分の考えを持ちながら、相手の考えにも耳を傾ける。その往復のなかで、対話は続いていきます。
共に働く仲間と意見が違っても、「この違いがあるからこそ、新しい発想が生まれる」と思えること。それが、関係の持続を信じるリーダーの姿です。
あなたは、どんな“違い”を抱えて、共に歩んでいますか?
違いを恐れず、相手の見ている世界に耳を傾ける。自分の考えを持ちながらも、他者の現実を否定しない。その両立の中にこそ、成熟したリーダーシップが宿ります。
🔗 関連記事: 誠実に関わり続ける──違いを越えて対話をつなぐリーダーシップ
✨ INNERSHIFTからのお知らせ
📘 公式サイト:innershift.jp
✍️ JOURNAL:innershift.jp/journal
🧭 Emotional Compass(2025年秋公開予定):innershift.jp/compass
🎥 YouTube:INNERSHIFT Channel
💼 LinkedIn:Yuta Mogami
🐦 X(旧Twitter):INNERSHIFT_JP
📘 Facebook:INNERSHIFT
📚 参考文献
- Isaacs, W.(1999)『対話する力(Dialogue and the Art of Thinking Together)』
- 最上雄太(2025)『人を幸せにする経営』(国際文献社)
→ https://amzn.to/4n7WstO