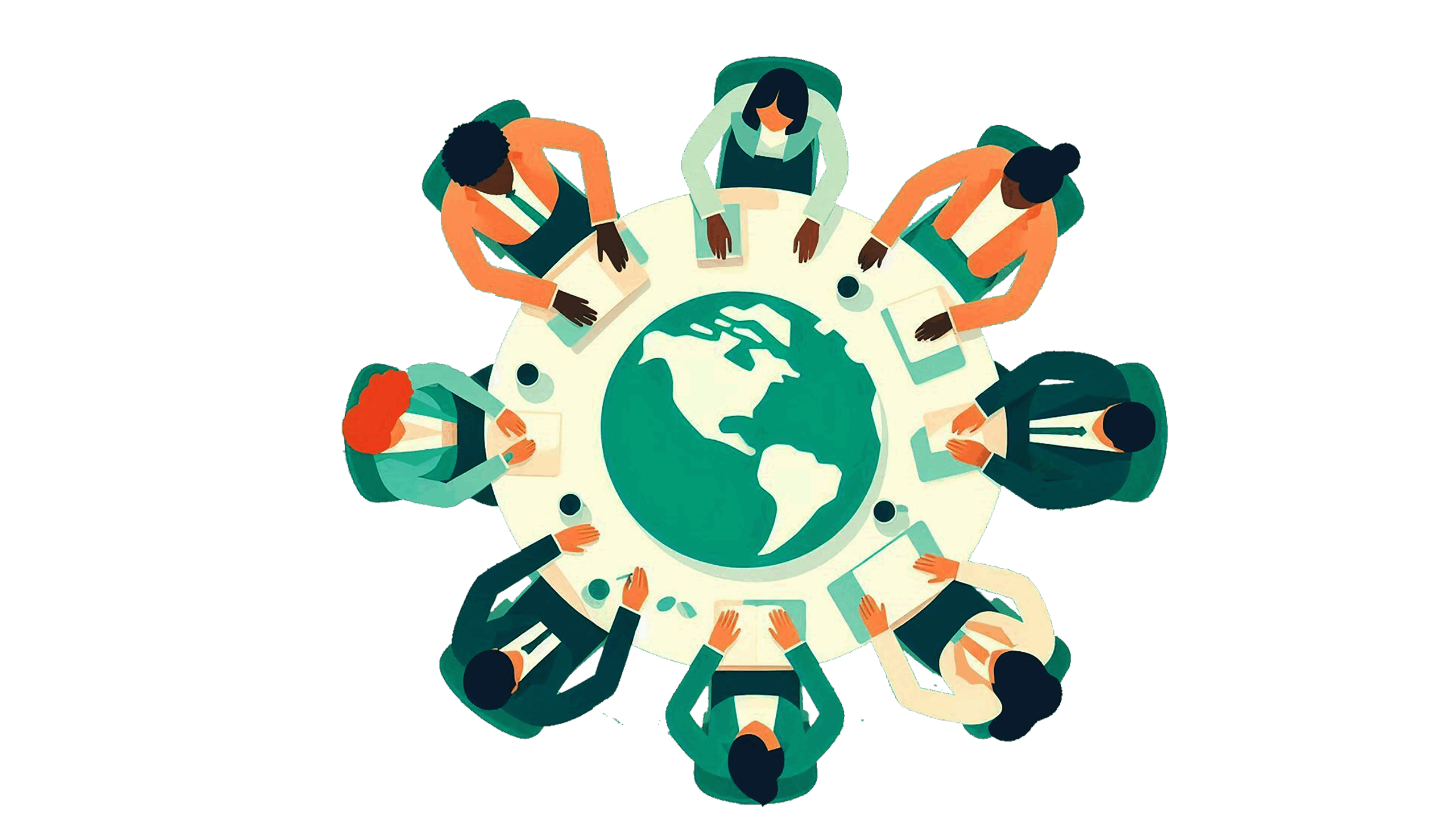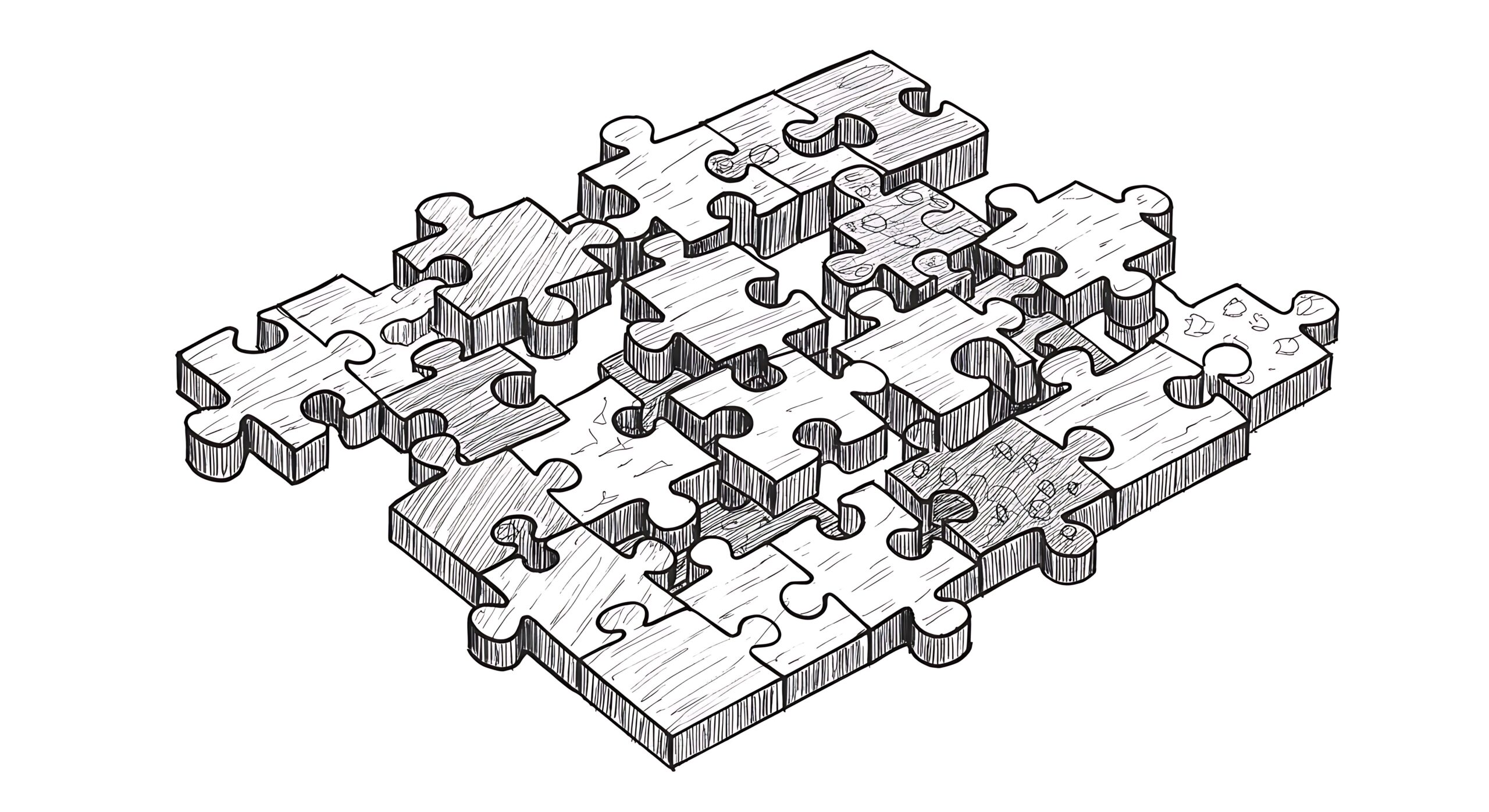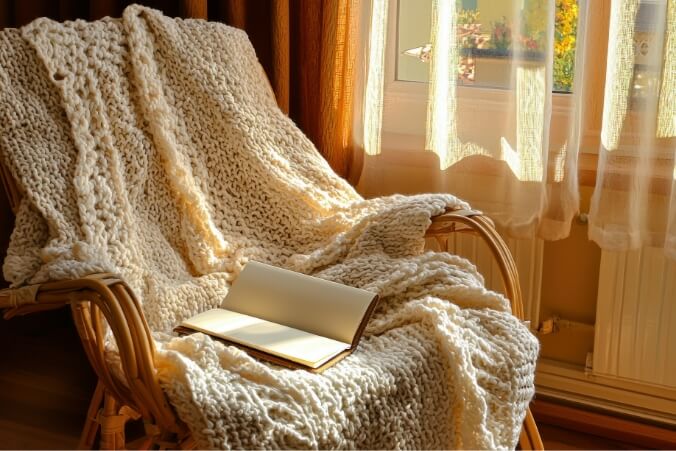すぐに答えを出さない勇気が、関係を深める
すぐに答えを出そうとする場面ほど、対話は浅くなってしまいます。意見がぶつかり、沈黙が流れると、「もう話しても意味がない」と思ってしまうことがあるかもしれません。けれども、本当の変化は、すぐに答えが出ない時間の中でしか生まれません。
対話とは、結論を急ぐことではなく、理解が深まるまで関わり続ける勇気です。意見が違っても、「話せば何かが生まれる」と信じる力──それが、リーダーの「差異への耐性」です。
Emotional Compassでは、本特性は関係管理(RM)因子に属します。
Emotional Compassでは、この特性を関係管理(Relationship Management/RM)因子に位置づけています。リーダーがすぐに判断せず、対話の流れを信じるとき、チームの中には安心と好奇心が広がります。差異への耐性とは、異なる考えを排除せず、“まだわからない”を共に受けとめる力なのです。
たとえば、議論が平行線をたどるとき。その場をまとめようとするよりも、いったん沈黙を受け入れる。その静かな余白の中にこそ、次の理解の種が芽生えていくのです。
対話とは、結論を保留する勇気である
ピーター・センゲ(Peter M. Senge)は『学習する組織(The Fifth Discipline)』(1990/再版2010)で、対話(Dialogue)をこう定義しています。
“In dialogue, people suspend assumptions and enter into a genuine thinking together.”
(対話とは、仮定を保留し、本当に共に考えることである。)
この“suspend assumptions(仮定を保留する)”という姿勢は、まさに「差異への耐性」の核心です。自分の前提をいったん横に置き、相手の言葉をそのまま受けとめる。そこには、すぐに評価しない勇気と、結論を急がない信頼があります。
センゲが語る対話は、「相手を説得するための会話」ではありません。むしろ、“わからなさ”を共に抱える時間のことです。違いの中にとどまりながら、新しい理解を生み出す──それが、学びと変化の出発点になります。
多様な意見が交わる組織では、すぐに答えを出そうとするほど、対話の可能性は狭まってしまいます。しかし、判断をいったん保留し、相手の意図や感情に耳を澄ませるとき、関係の中に「まだ見ぬ理解」が生まれるのです。
“違い”とは、結論を阻む壁ではなく、新しい思考が芽生える余白です。その余白にとどまり続ける力こそが、リーダーの「差異への耐性」です。
わからなさの中で、関係を信じ続ける力
ピーター・センゲが語る“対話の勇気”は、INNERSHIFTが描くリーダー像とも重なります。最上雄太(2025)『人を幸せにする経営』(国際文献社)では、こう述べられています。
「リーダーは、意見の一致よりも、対話の継続を信じることが大切だ。」
この言葉は、差異への耐性を「信頼を絶やさない姿勢」として再定義しています。意見の違いがあるからこそ、対話を続ける価値がある。結果を急がず、理解が形になるまで関わり続けること──それが、関係を成熟させるリーダーの在り方です。
差異に耐えるとは、我慢することではなく、「理解が生まれるまで待つ」こと。すぐに解決しようとせず、相手の言葉が自分の中で熟していく時間を許すこと。その静かな時間の中で、信頼は少しずつ、確かなものになっていきます。
対話には、結論よりも「つづき」があります。たとえ意見が交わらなくても、「話せば何かが生まれる」と信じて関わり続けることが、リーダーとしての誠実さであり、人をつなぐ知性です。
あなたは、どんな“わからなさ”に、とどまり続けられますか。
🔗 関連記事:誠実性──違いと関わり続ける力が、信頼を育てるリーダーシップ
参考文献
- ピーター・センゲ(1990/再版2010)『学習する組織(The Fifth Discipline)』Doubleday.
- 最上雄太(2025)『人を幸せにする経営』(国際文献社)https://amzn.to/4qezqDH
✨ INNERSHIFTからのお知らせ
📘 公式サイト:innershift.jp
✍️ JOURNAL:innershift.jp/journal
🧭 Emotional Compass(2025年秋公開予定):innershift.jp/compass
🎥 YouTubeチャンネル:INNERSHIFT Channel
💼 LinkedIn:Yuta Mogami
🐦 X(旧Twitter):INNERSHIFT_JP
📘 Facebookページ:INNERSHIFT