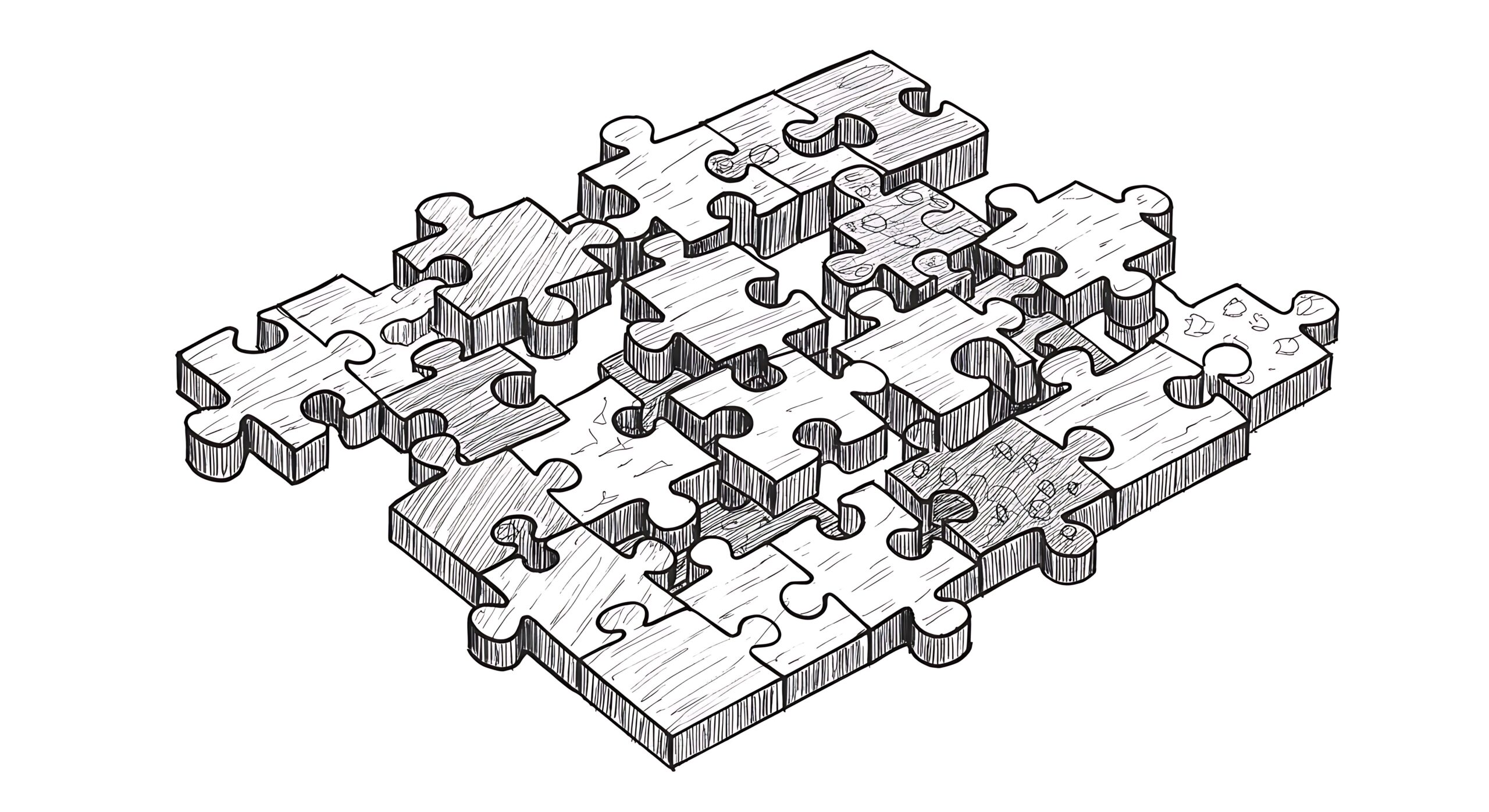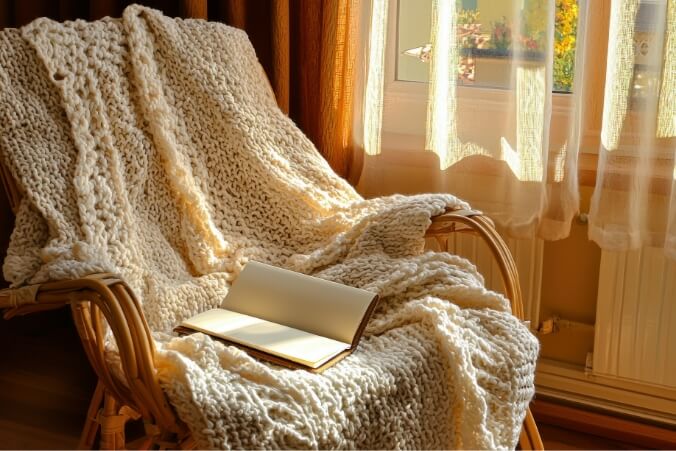朝、同じ会議室で話していても、話がかみ合わないことがあります。相手は自分と違う前提で話しているように感じ、自分の言葉も届かない。その瞬間、私たちは気づきます。「対話」とは、相手を変えることではなく、自分の考えが揺らぐ時間なのだと。
「対話期待性」とは、他者との関わりの中で自分の考えが変化していく可能性を信じる力です。それは、説得でも迎合でもなく、“わからなさ”を抱えたまま共に考える姿勢。Emotional Compassでは、本特性は関係管理(RM)因子に属します。リーダーは「答えを持つ人」ではなく、「問いを開き続ける人」なのです。
正しさの外に出る勇気
人は誰しも、自分の考えが正しいと思いたいものです。けれど、正しさにとらわれると、対話は防衛の場になります。自分を守るために話すと、相手の声は届かなくなる。その瞬間、関係の可能性が閉じてしまうのです。
リーダーシップの成熟とは、自分の正しさを一度疑うこと。「もしかしたら、違うかもしれない」と思える瞬間に、対話は新しい命を吹き返します。それは、自分の信念を捨てることではなく、他者の言葉を通して信念を磨き直すことです。
「対話」は新しい意味を共に生み出す行為
物理学者デイヴィッド・ボーム(Bohm, 1996)『On Dialogue(対話について)』はこう語ります。
「対話とは、個人の思考を超えて、新しい意味を共に生み出す行為である。」
この「共に生み出す」という視点は、対話を“勝ち負け”や“理解の一致”から解放します。異なる意見のあいだにこそ、新しい洞察が宿る。ボームの言葉は、リーダーが“わからなさ”にとどまる勇気をもつことの重要性を示しています。
対話の価値は、相手を理解しきることではありません。むしろ、理解しきれないことを受け入れながら、そのなかで生まれる「変化の兆し」を見逃さないこと。それが、対話に期待するという成熟の知性です。
「わからないまま話す」ことから信頼は始まる
最上雄太(2025)『人を幸せにする経営』(国際文献社)では、こう語られています。
「わからないまま話すことが、信頼の始まりである。」
すぐに結論を出さずに、話しながら考える。その“未完成の時間”にこそ、関係は育ちます。対話とは、理解を完成させるためではなく、共に揺らぐためのプロセスなのです。
職場で意見が衝突するとき、リーダーが見せるべきは正解ではなく、問いを持ち続ける姿です。「どうしてそう思うのだろう?」と耳を傾ける姿勢が、チーム全体に“考え続ける文化”を育てていきます。
「わからなさ」を希望として抱く
対話期待性とは、他者と出会うたびに、自分が変わりうることへの信頼です。対話とは、未来に向けて開かれた知的冒険。完全な理解よりも、変化し続けることを選ぶ勇気に、リーダーの成熟は宿ります。
私たちは、対話を通して世界の見方を更新していく存在です。だからこそ、“わからない”という感覚を恐れる必要はありません。それは、変わり続ける自分と出会うチャンスなのです。
あなたは、どんな“わからなさ”と共に話していますか?
🔗 関連記事: 同じ景色を見ていても、感じているものは違う──「差異」を受け入れるリーダーシップ
✨ INNERSHIFTからのお知らせ
📘 公式サイト:innershift.jp
✍️ JOURNAL:innershift.jp/journal
🧭 Emotional Compass(2025年秋公開予定):innershift.jp/compass
🎥 YouTube:INNERSHIFT Channel
💼 LinkedIn:Yuta Mogami
🐦 X(旧Twitter):INNERSHIFT_JP
📘 Facebook:INNERSHIFT
📚 参考文献
- Bohm, D.(1996)『On Dialogue(対話について)』Routledge.
- 最上雄太(2025)『人を幸せにする経営』(国際文献社)
→ https://amzn.to/4n7WstO