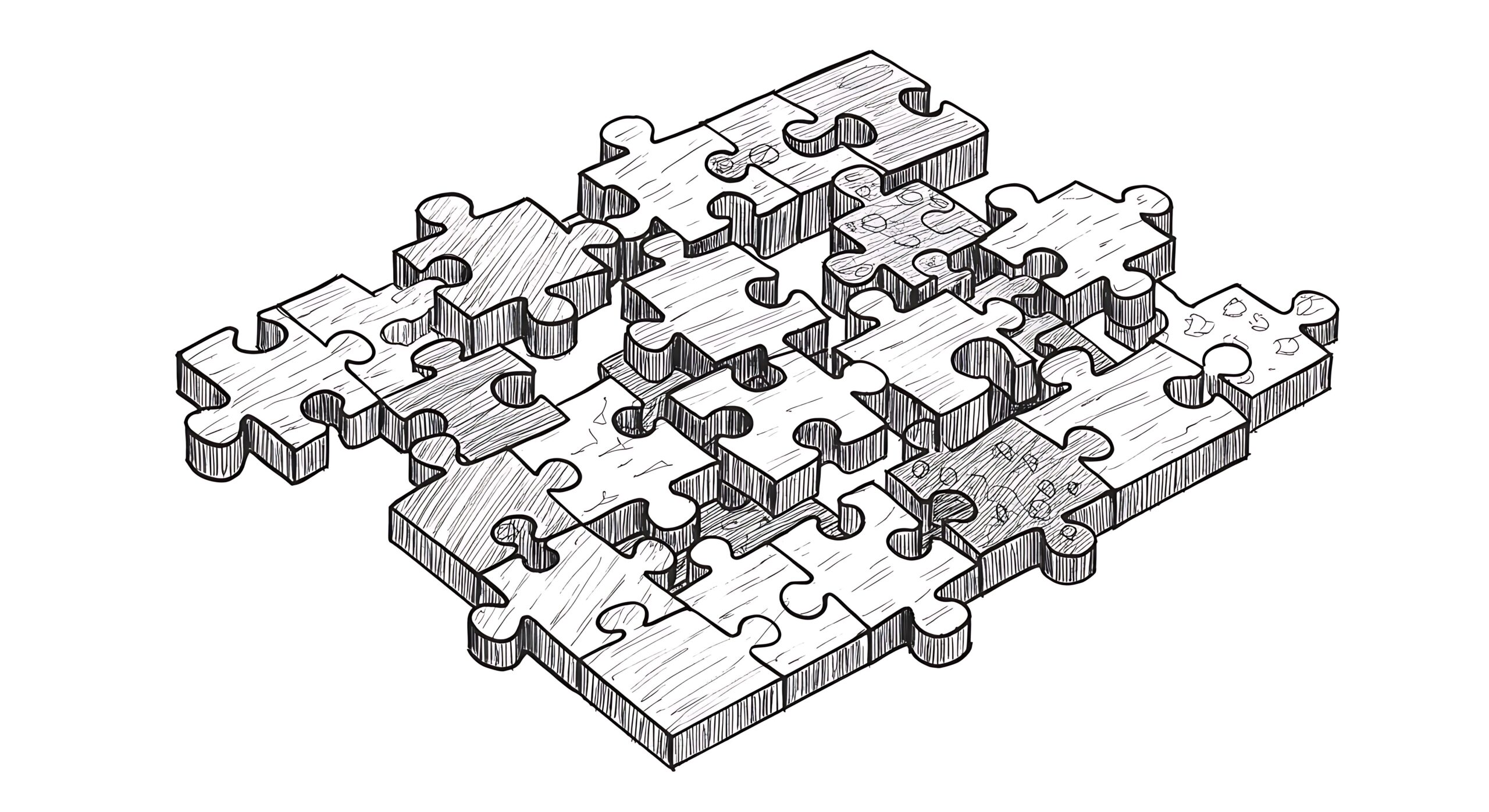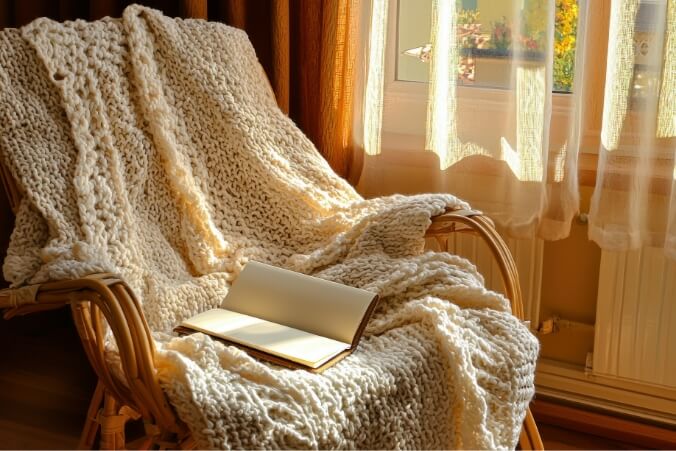対話期待性とは
会議や話し合いで「誰かが声をかけてくれるのを待ってしまった」経験はありませんか。自分の考えを伝えたい気持ちはあっても、きっかけがつかめず、発言を控えてしまう場面は誰にでもあります。
対話期待性とは、自分から積極的に対話を始めるのではなく、相手からのアプローチや場の雰囲気に応じて対話に入っていく傾向を指します。
Emotional Compassでは、本特性は関係管理(RM)因子に属します。特性です。対話期待性が弱めの傾向があると、発言や関わりが受け身になりやすく、対話の機会を逃すことがあります。しかし、これは必ずしも弱みではなく、相手をよく観察し、タイミングを見極める「慎重さ」や「場を読む力」として働くこともあります。
リーダーにとって、対話を待つ姿勢だけではなく、自ら対話を生み出す力が求められます。小さな一言でも、自分から声をかけることでチームの安心感や協力意識が高まり、関係性が強まります。対話を生み出す姿勢は、心理的安全性を育て、組織を前向きに動かす原動力となります。
研究が示す対話期待性の力
心理学の研究では、対話や相互理解が信頼を育む重要な要素であることが示されています。たとえば心理学者エイミー・エドモンドソンは、心理的安全性の研究の中で「安心して声を上げられる環境」がチームの学習や協力に直結すると指摘しました。これは、受け身の姿勢から一歩踏み出し、対話を始めることの重要性を裏づけています。
実務の現場でも、ハーバード・ビジネス・レビュー(HBR)の記事
『聞く力が人を変える(The Power of Listening in Helping People Change)』(イツチャコフとクリューガー, 2018)は、リーダーが真摯に耳を傾けることで、相手の自己開示や変化を促すと指摘しています。これは、ただ対話を待つのではなく「相手の声に丁寧に耳を傾ける姿勢」から積極的な対話が生まれることを示しています。
経営学の観点では、最上雄太(2022)が『シェアド・リーダーシップ入門』の中で「対話を通じた意図の共有」がチームの協働を深めると論じています【Amazon】。また近著(2025)『人を幸せにする経営』では、リーダー自身が対話を先導することで「心理的安全性と成果の両立」を実現できると強調しています【Amazon】。
実践のためのレシピ
対話期待性が弱めの傾向があるときでも、次の工夫で「自ら対話を生み出す一歩」を踏み出すことができます。
- 相手の発言に質問を返す
すぐに自分の意見を言わなくても、「それはどういう意味?」と尋ねるだけで対話の流れをつくれる。 - 小さな共有から始める
自分の考えをすべて語らなくても、「私も同じ経験があります」と短い一言を添えることで会話が広がる。 - 相手の言葉を言い換える
「つまり◯◯ということですね」と確認するだけで、相手に理解が伝わり、対話が深まる。 - 定期的に振り返りの場を持つ
週1回でも「最近気づいたこと」を共有する習慣をつくると、自然に対話が定着する。
信頼を育むリーダーへ
リーダーが自ら対話を生み出す姿勢を示すと、メンバーは「自分の声を受け止めてもらえる」と感じ、安心して意見を表明できるようになります。これは心理的安全性を高め、チームの多様な視点を生かす土台になります。
一方で、相手の反応を待つだけではなく、自ら問いかけや共有を行うことで、チームに「対話が当たり前の文化」を根づかせることができます。その姿勢が、協働を促し、信頼関係を強めるリーダー像へとつながります。
あなた自身は?
最近、会議や対話の場で「誰かの声を待ってしまった」経験はありませんか?
そのときに、自分から一言でも声をかけていたら、どんな変化が生まれたでしょうか。
次に同じような場面に直面したとき、あなたはどんな一歩を踏み出したいですか?
さらに詳しく学びたい方へ
- 🧭 Emotional Compass(自己特性診断|2025年秋公開予定)
👉 https://innershift.jp/compass/ - 📘 書籍『人を幸せにする経営』(2025)
👉 https://amzn.to/4n7WstO - 📘 書籍『シェアド・リーダーシップ入門』(2022)
👉 https://amzn.to/3IqOixG
✨ INNERSHIFTからのお知らせ
📘 公式サイト:innershift.jp
✍️ JOURNAL:innershift.jp/journal
🧭 Emotional Compass:innershift.jp/compass
🎥 YouTubeチャンネル:INNERSHIFT Channel
💼 LinkedIn:Yuta Mogami
🐦 X(旧Twitter):INNERSHIFT_JP
📘 Facebookページ:INNERSHIFT
参考・出典
- Edmondson, A. (1999). Psychological safety and learning behavior in work teams. Administrative Science Quarterly.
- Harvard Business Review, 『聞く力が人を変える(The Power of Listening in Helping People Change)』, イツチャコフ & クリューガー, 2018|https://hbr.org/2018/05/the-power-of-listening-in-helping-people-change
- 最上雄太(2022)『シェアド・リーダーシップ入門』(国際文献社)|https://amzn.to/3IqOixG
- 最上雄太(2025)『人を幸せにする経営』(国際文献社)|https://amzn.to/4n7WstO