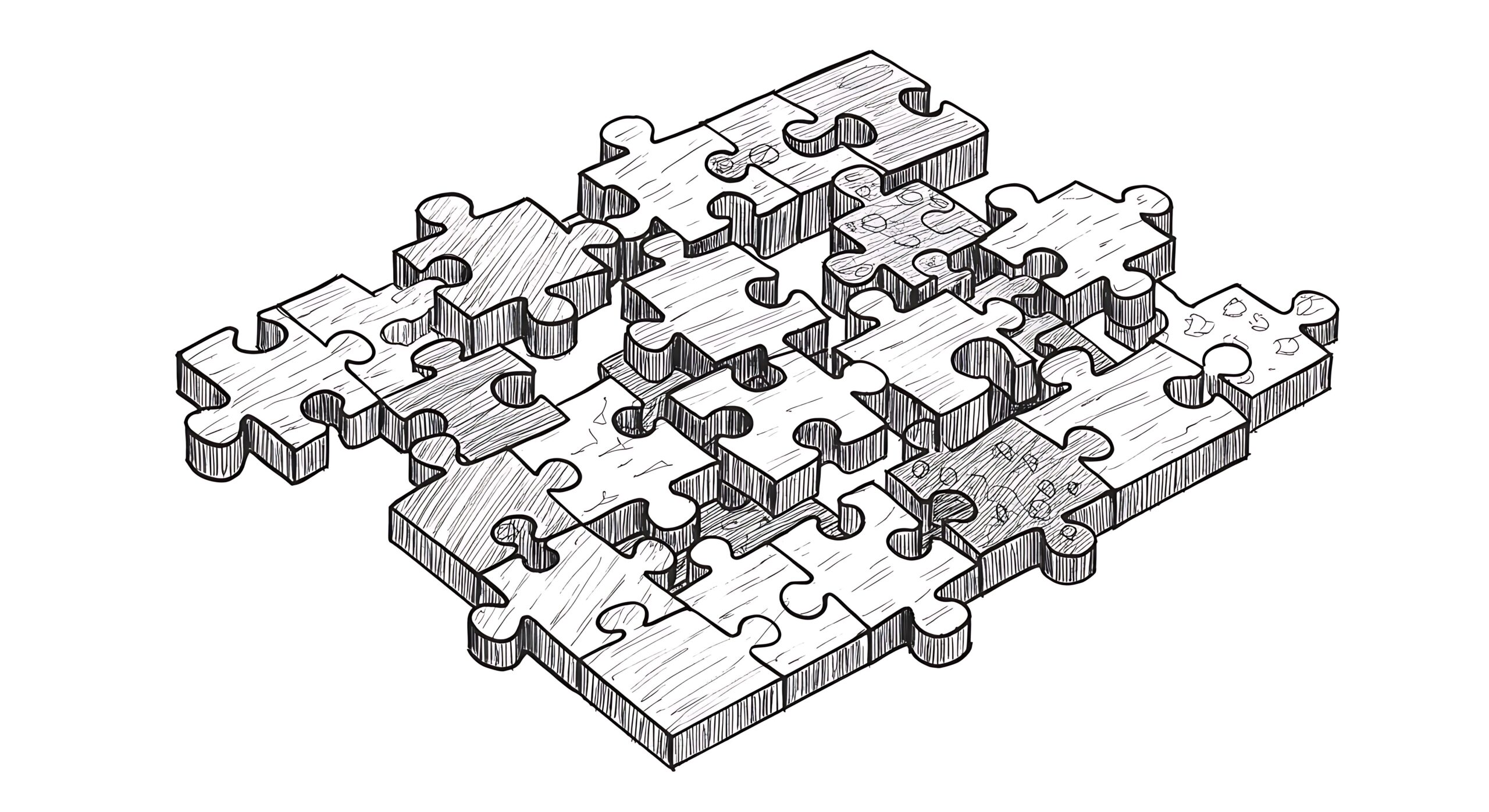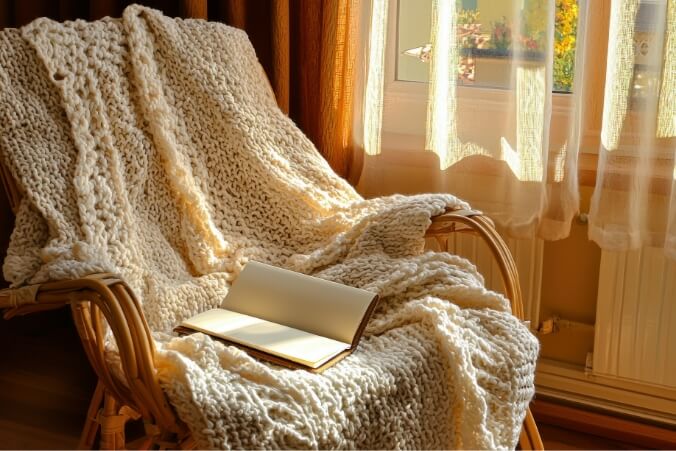自分の行動に「理由」を持つということ
「なぜこの仕事をしているのか」。その問いへの答え方は、リーダーの成熟度を映す鏡です。動機を外から与えられたものとして受け取るか、それとも自分の内側で再定義するか。そこに、リーダーシップの深度の違いが現れます。動機探索力とは、目標の達成意欲ではなく、行動の“理由”を見つめ直す知的な内省力です。Emotional Compassにおいて、この力は自己認識(Self-Recognition)の中核に位置づけられています。自分の価値観・感情・目的を見つめ直し、それらを統合することで、言葉と行動の一貫性を育てる力です。動機の根を深く掘るほど、リーダーは迷いに強く、周囲に安心と説得力をもたらします。
Emotional Compassでは、本特性は自己認識(SA)因子に属します。
意味を再定義する内的エネルギー
外から与えられた目標や報酬ではなく、「自分が本当に大切にしたい価値」によって動くとき、人の行動は静かな持続力を帯びます。ダニエル・ピンク(Pink, 2009)は『Drive』で、人を動かす本質的な力は「自律」「熟達」「目的」の三つにあると述べました。特に“Purpose(目的)”は、行動の意味を自ら定義し直すことで生まれる内発的なエネルギーです。評価や指示に左右されず、自分の「意味」に根ざして行動する姿勢が、成熟したリーダーを形づくります。
「意味」に生きるという選択
もうひとつの視点として、ヴィクトール・フランクル(Frankl, 1946)は、古典的な名著『夜と霧(Man’s Search for Meaning)』で、人は「目的」ではなく「意味」によって生きる存在だと説きました。どんな状況にも“意味を見出す自由”があるという彼の洞察は、現代のリーダーにも深く響きます。環境や他者の期待ではなく、「自分は何に価値を見いだし、どんな意図で行動しているのか」を問い直すことが、リーダーの内的成長を支えます。
動機を語るリーダーが信頼を生む
最上(2022)『シェアド・リーダーシップ入門』では、「意味の内面化」をキーワードに、リーダーが自分の動機を語れることが、他者の共鳴を生むと述べています。つまり、動機探索力の高いリーダーは、自分のWhyを語ることで、チームのWhyを呼び覚ます存在です。さらに最上(2025)『人を幸せにする経営』では、行動の一貫性と説得力の源泉を“個人の価値観と組織の目的を重ね合わせること”に見いだしています。
5分の「Whyメモ」がもたらす変化
日々の行動を少し立ち止まって、「なぜこの選択をしたのか」と言葉にしてみる。たとえば、週末5分の「Whyメモ」を書いてみるだけでも、自分の行動の背景にある価値観が見えてきます。リーダーが自分の理由を見つめ直すことは、チームの方向性を静かに整える行為です。行動の理由を探ることは、過去を掘り返すことではなく、未来の一貫性をつくることです。
まとめ
動機探索力の成熟とは、外から与えられた理由を生きるのではなく、自らの内側で「意味」を見出すことです。自分の行動の根にある価値を言葉にできるリーダーは、迷いの中でも一貫した道を歩み、周囲の人の意志を照らします。行動の理由を問うことは、自分の存在理由を編み直すこと。あなたの動機が誰かの希望へとつながるとき、リーダーシップは静かに完成します。
✨ INNERSHIFTからのお知らせ
📘 公式サイト:innershift.jp
✍️ JOURNAL:innershift.jp/journal
🧭 Emotional Compass:innershift.jp/compass
🎥 YouTubeチャンネル:INNERSHIFT Channel
💼 LinkedIn:Yuta Mogami
🐦 X(旧Twitter):INNERSHIFT_JP
📘 Facebookページ:INNERSHIFT
📚 参考文献
Frankl, V. E. (1946). Man’s Search for Meaning. Beacon Press.
Pink, D. H. (2009). Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us. Riverhead Books.
『人を幸せにする経営』(最上雄太, 2025, 国際文献社) → Amazonリンク
『シェアド・リーダーシップ入門』(最上雄太, 2022, 国際文献社) → Amazonリンク