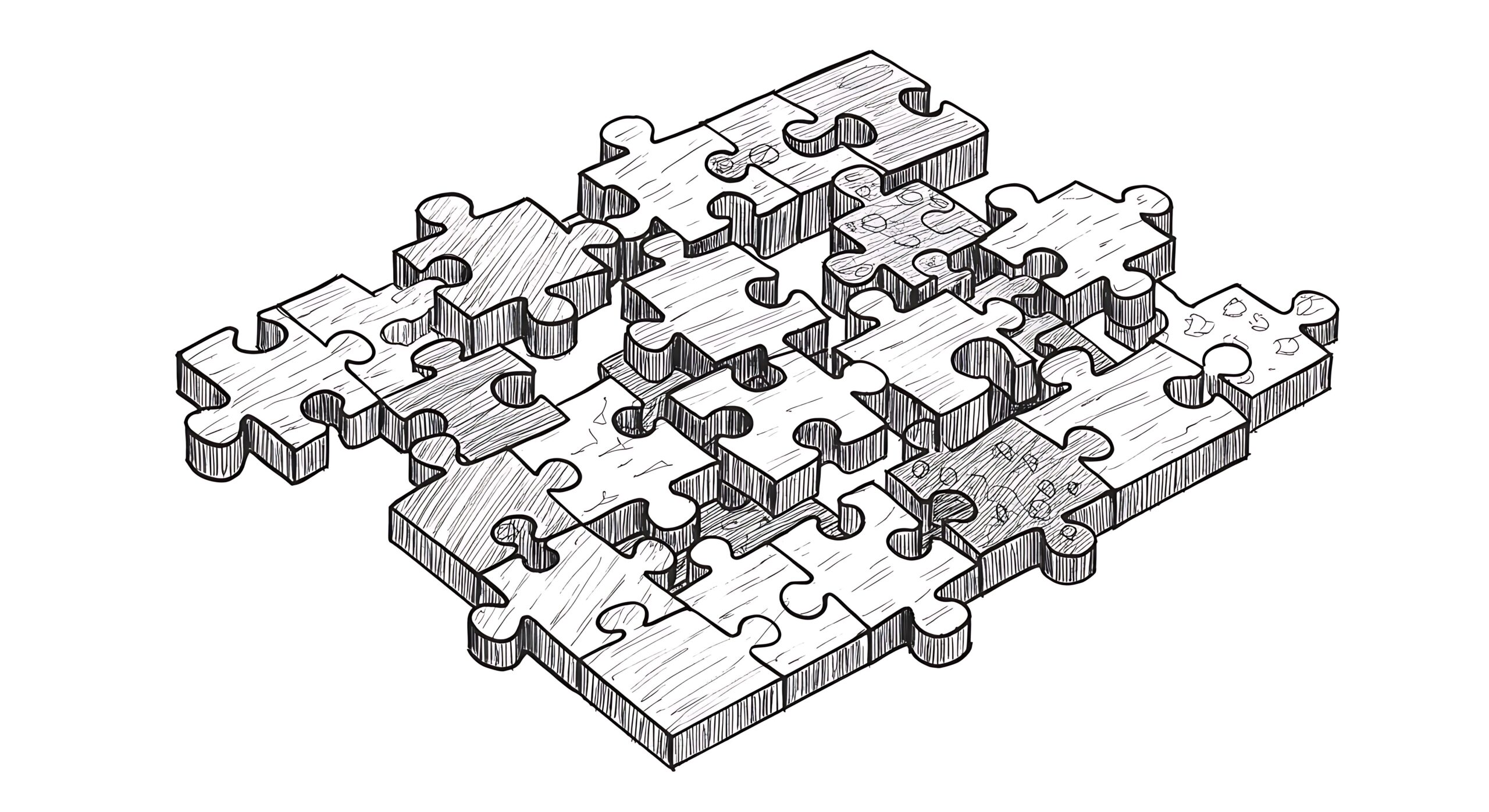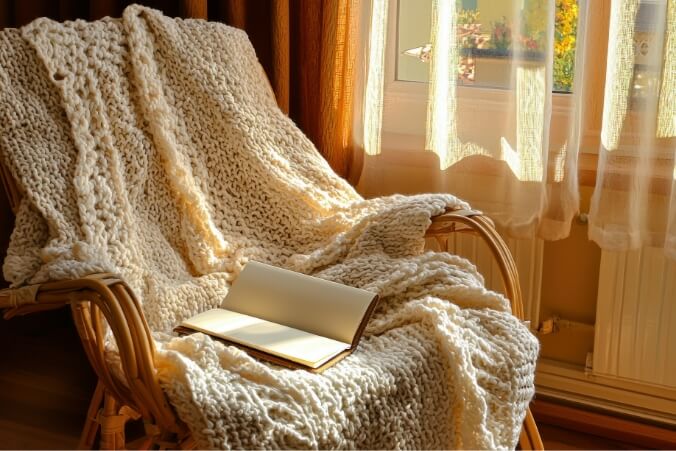感じ取る力とともに生きる
誰かの沈黙、微かなため息、声の揺らぎ。そうした小さなサインに心を動かされる瞬間があります。人の感情を感じ取る力は、美しく、そしてときに苦しい。優しさゆえに、他者の痛みに引き寄せられ、自分まで疲れてしまうこともあるでしょう。
けれど、共感は弱さではありません。それは、相手の存在を大切に思う心の証。共感的感度とは、相手の感情を“そのまま背負う”のではなく、響き合いながらも自分を保つ力のことです。
Emotional Compassにおいて、この力は関係管理(Relationship Management)の中核を担います。他者の感情を察しながらも、自分の静けさを失わず、関係に調和を生み出す。それが、リーダーとして信頼を築く最初の一歩です。
Emotional Compassでは、本特性は社会的認識(SO)因子に属します。
感受から共鳴へ──成熟した共感のかたち
共感には、二つの段階があります。ひとつは、相手の感情を“感じ取る”感受的共感。もうひとつは、感じ取った感情をもとに“関係を深める”共鳴的共感です。前者は感情の共有、後者は関係の創造です。
ダニエル・ゴールマン(Goleman, 1995)は『Emotional Intelligence』の中で、共感を「他者の感情を理解するだけでなく、それにふさわしく反応できる力」と定義しました。共感は受動的な感受性ではなく、能動的な関係構築の知性なのです。
たとえば、部下の戸惑いを察してすぐに助言することが最良とは限りません。むしろ、言葉を待ち、相手が自分で整理できる空間を保つこと――その沈黙の中にこそ、信頼の芽が育っていきます。
感じすぎる優しさを整える
共感的感度が高い人ほど、他者の感情を細やかに受け取り、深く共鳴します。それはリーダーとしての強みである一方、心が疲弊しやすい側面もあります。相手の悲しみや焦りを“自分ごと”として抱え込むと、いつのまにか境界が曖昧になり、内なるバランスを失ってしまう。
そのときに大切なのは、「共感すること」と「同化すること」を分けて考えることです。相手に寄り添いながらも、自分の静けさを守る。その余白があるからこそ、リーダーは他者の感情を正確に受け止め、チーム全体を穏やかに整えることができるのです。
思想の橋渡し:分かち合いの知性としての共感
最上雄太(2022)『シェアド・リーダーシップ入門』では、共感を「他者の感情を分かち合い、関係の中で新しい理解を生み出す知性」として位置づけています。共感とは、相手の世界に入り込むことではなく、世界を一緒に見つめ直す行為。その姿勢が、チームに安心と創造性をもたらします。
静かに相手を見つめ、すぐに答えを出さず、ただ一緒にその感情のそばにいる。リーダーの共感的感度とは、言葉よりも「在り方」で伝わる力なのです。
まとめと問い:静かな理解が、信頼を育てる
共感は、感じ取る力であると同時に、関係を整える力でもあります。相手の感情を抱え込みすぎず、響き合う距離を見つけること。そこに、成熟したリーダーの優しさが宿ります。
次に誰かの沈黙に出会ったとき、あなたはどう受け取りますか。
そ
✨ INNERSHIFTからのお知らせ
📘 公式サイト:innershift.jp
✍️ JOURNAL:innershift.jp/journal
🧭 Emotional Compass:innershift.jp/compass
🎥 YouTubeチャンネル:INNERSHIFT Channel
💼 LinkedIn:Yuta Mogami
🐦 X(旧Twitter):INNERSHIFT_JP
📘 Facebookページ:INNERSHIFT
📚 参考文献
- Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence. Bantam Books.
- 最上雄太(2022)『シェアド・リーダーシップ入門』(国際文献社)|https://amzn.to/3IqOixG