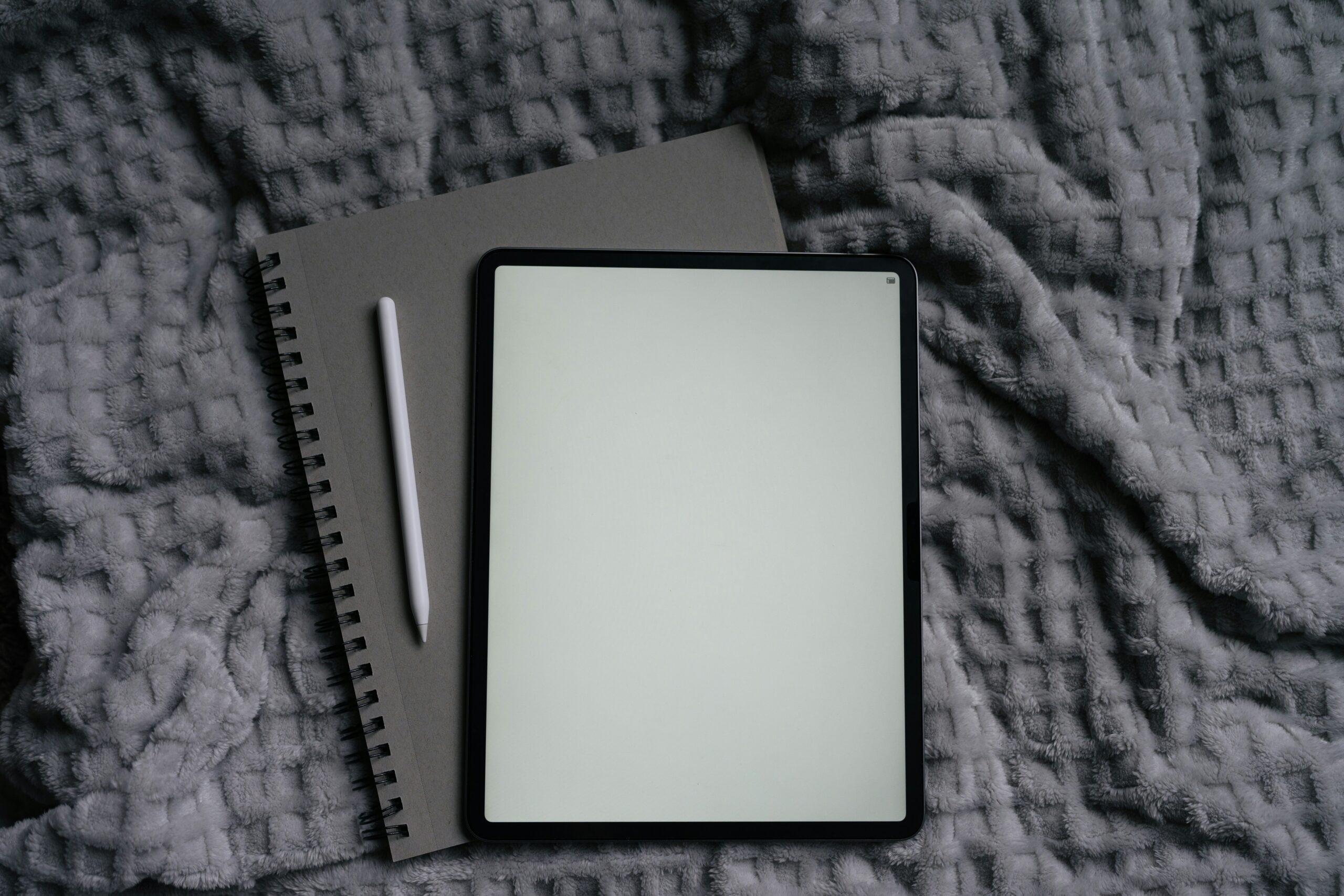
📎 参考|研究と実践のあいだで──noteで綴るINNERSHIFT
経営学の研究と現場の対話、その“あいだ”に生まれる気づきを綴るnote。リーダーシップ、感情知性、組織変容といったテーマに加え、INNERSHIFTの構想や舞台裏もリアルに共有しています。静かな伴走を大切にしながら、問い […]
INNERSHIFTの源流には、感情・行動・関係の“見えにくいプロセス”を丁寧に見つめ続けてきた
最上雄太の研究と実践があります。
このページでは、その背景にある問いや、支援思想の起点をご紹介します。
現場の問いから立ち上がったリーダーシップ論
INNERSHIFTは、「感情から行動が生まれ、行動から関係が育ち、その関係が組織や社会を動かしていく」というプロセスを丁寧に捉えるところから始まりました。リーダーシップを、特別な誰かの資質ではなく、関係の中で立ち上がる現象としてとらえ直す試みです。
企業や大学院での支援のなかで、「なぜ、同じ施策でもチームによって結果が違うのか」「なぜ、一部の人だけが負荷を背負ってしまうのか」といった問いが繰り返し現れました。それらに向き合う中で、感情・ふるまい・関係性のあいだにある“見えにくいプロセス”を言葉にし、構造として捉え直す必要性が見えてきました。
Emotional Compass や IS360、INNERSHIFT JOURNAL といったモジュールは、こうした現場の問いと博士研究の往復から生まれた「対話のための装置」です。本ページでは、その設計を担う最上雄太の背景と、支援の原点をご紹介します。
INNERSHIFTの思想と設計背景については、こちらの動画でも紹介しています。
INNERSHIFTとは何か(動画を見る) →
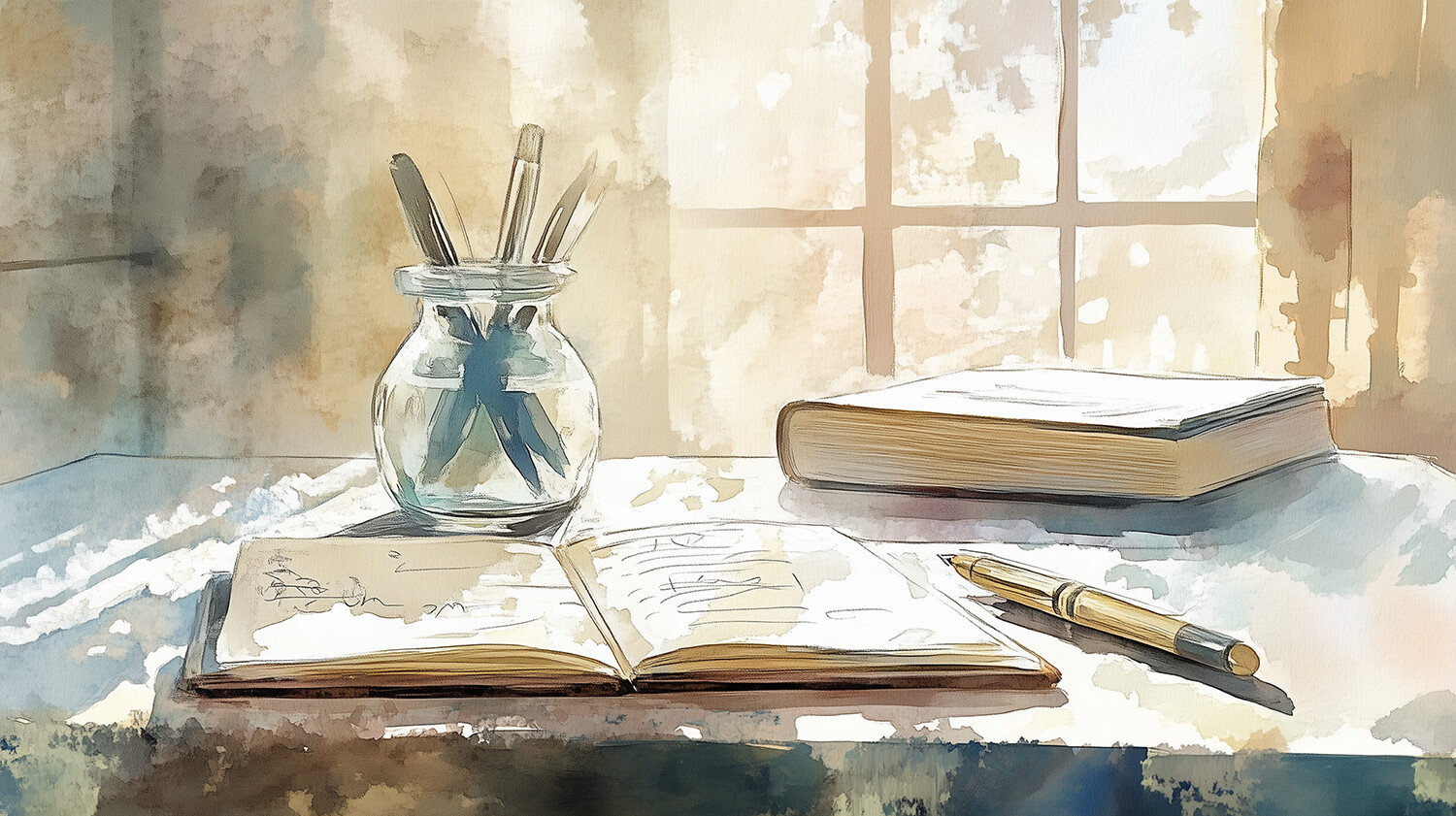
最上雄太は、リーダーシップ研究を専門としながら、企業や社会人大学院などで30年以上にわたり実務支援を行ってきました。
博士研究では「シェアド・リーダーシップ」の発生メカニズムとその理論的基盤を明らかにし、現場実践と学術的知見による支援モデルを構築してきました。
著書には『人を幸せにする経営』(2025)、『シェアド・リーダーシップ入門』(2022)があります。
これらの知見は、INNERSHIFTの核となる「Emotional Compass(自己特性診断)」や「INNERSHIFT JOURNAL」に反映されています。
詳しいプロフィールや最新の活動は LinkedIn にてご覧いただけます。
「贈るリーダーシップ」の背景については、書籍制作に込めた意図を紹介した
動画でも詳しく語っています。
贈るリーダーシップ(動画を見る) →

このページに関連する特集記事をご紹介いたします